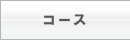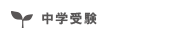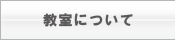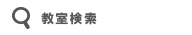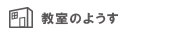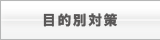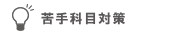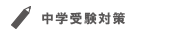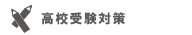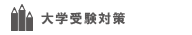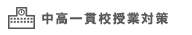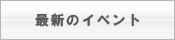���m�点�y���E�� ���z
�V��3����3���̂���������g��łق�����
����ɂ��́B�m�[�o�X�̍�����i�͂�����j�ł��B
�R���������߂��܂����B�����ɂ͐V�w�����n�܂�܂��B�B
�V���w�Z�R�N���ɂƂ��ẮA����܂łɌo���������Ƃ̂Ȃ��P�N�ԂɂȂ�Ǝv���܂��B
�w�Z�����̖ʂł͍ŏ㋉���ƂȂ�A�l�X�ȍs�����ƂŃ��[�_�[�Ȃǂ̂܂Ƃߖ��ƂȂ�A�������ł��S�̂����[�h���Ȃ���Ȃ�܂���B
���ꂩ��C�w���s������A�^�����ɏ������Ă��鐶�k�͉Ă̌����A�֓����A�S�����ւƌq����傫�ȑ����T���܂��B
�X�ɕ��ʂł́A����e�X�g�̑��ɖk�C�e�X�g��������āA�قږ����̂悤�Ƀe�X�g���邱�ƂɂȂ�܂��B�������邾���ł͂Ȃ����ʂ��d�v�ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA���܂ňȏ�Ɍv��I�ɃR�c�R�c�Ƃ���Ă����K�v������܂��B
�Z�����̃��Y�������
�P���̐����̃��Y�������܂��傤�B�Ⴆ�Ε�������A���ė��āA�V���̗[�H�܂ł͎��R�ɉ߂����B���т�H�ׂ���m�֍s���ĂV��������P�O���܂ŕ�����B�A���Ă����炨���C�ɓ����Ė����̏����𐮂��ĂP�Q���܂łɐQ��A�Ƃ�����ɁA�u�����ԑсv�Ɓu���R���ԑсv�����߂�悤�ɂ��܂��傤�B
�u���Ԃ̂��鎞�ɋC��������������悤�v�Ƃ����悤�ȑԓx���ƁA�e�X�g���O�ɂȂ��čQ�ĂȂ�����������邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B���Ԃ������ĉɂ�����Q�[��������A�X�}�z��������A�ƂȂ��Ă��܂������ł��B�Q�[����X�}�z���֎~�Ƃ���K�v�͂���܂��A�u���R���ԑсv�Ƀ��t���b�V���̂��߂Ɏg���ĉ������B
�Z�k�C�e�X�g�ƒ���e�X�g�͓������炢�厖�I
�R�N���ɂȂ�ƒ���e�X�g�Ɩk�C�e�X�g�̂Q�̑傫�ȃe�X�g�Ɍ����Ċw�K��i�߂Ȃ�������܂���B
�u�ǂ������厖�ł����H�v
�Ƃ������k�i����j�𑽂���̂ł����A�ǂ�����d�v�ł��B�ǂ��炩������Ă悢�A�Ƃ������Ƃ͂���܂���B�ł�����o�����X�悭�����Ăق����̂ł����A�o�����X�̎������悭�킩��Ȃ��Ƃ������k�������Ǝv���܂��B����Ȑ��k�͐���ȉ��̂悤�ɂ��ĉ������B
�Z���o�����X�̂Ƃ��
�@�����͖k�C�e�X�g�i�����̕M�L�����j�Ɍ�������������i�P�A�Q�N���̕��K�A���K�j�B
���j���ɂ���ĕ����鋳�Ȃ����߂�̂����ʓI�ł��B�Ⴆ�Ό��j���́u���w2���ԁA���ȂP���Ԃ��v�Ηj���́u�p��̒������1���ԂƎЉ�̗��j2���Ԃ��v�ȂǁB�����g���ȖځA�P���ƈËL�̉ȖڒP����g�ݍ��킹��Ɩ����Ȃ����ł��܂��B
�A�y�����g���Ĉ�T�Ԃ̂����Ɋw�Z�Ői�͈͂̃m�[�g�܂Ƃ߂�[�N�̉��K���s���B�����ĕ����ɉ��������W�����K�i���������j���s���B
�B����e�X�g�Q�T�ԑO����͒���e�X�g�͈͂̕��ɓO����B
�ȏ�́A������w�̂Ƃ��Ɏ��H���Ă������v��̗��ĕ��ł��B�@�ŋ��Ȃ̕����Ԃ̃o�����X���Ƃ�܂��B�A�Łu���K�i���������j�v���s���̂́A�u�V�����o���邱�Ɓv�Ɓu�o�������Ƃ�Y��Ȃ��悤�ɂ��邱�ƁA�蒅�����邱�Ɓv�̃o�����X���Ƃ邽�߂ł��B
���l�Ԃ̔]�͏��߂Ċo�������Ɓi���������Ɓj�̂U�`�V������T�Ԉȓ��ɖY��܂��I�@
���x�����K���邱�ƂŋL���͖Y��ɂ����Ȃ�܂��B3��ȏ�͌������������������܂��傤�B
�A�ł̒���e�X�g��̕��K���B�ɊY�����܂��B
�V���R���̕��ŕ��̂��Ƃ�̂��Ƃł��Y�݂̂��Ƃ�����܂�����A���⍇���������B���m�ł͊w�K�J�E���Z�����O���s���ċ�̓I�ȉ����Ă�����Ă��Ă���܂��B
�����k�E���⍇����
�s�d�k�@048-859-7137
�܂�
���E�� ��� [2019-03-16]
��ʌ��������Z�����̔{�����m�肵�܂����B
2/22�Y�ŁA�R�P�N�x�̍�ʌ��̌������Z�����̔{�����m�肵�܂����B
�e���Z�w�ȁE�R�[�X�̔{���͈ȉ��̃����N����m�F�ł��܂��B
http://www.navi.spec.ed.jp/w/MapSearch.aspx
�{���̍���͎��ɂƂ��ċC�ɂȂ���̂ł��傤�B���ɍ��Z�����߂Ă̎ƂȂ���ɂƂ��Ă͎������Ȃ̂�������܂���B�������A�K�v�ȏ�ɋ����K�v�͂���܂���B�k�C�e�X�g���Łu���i���v�̔�������ē����ɗՂ�ł���Ȃ�A���͈ȏ�̗͂��o���炸�Ƃ����i�ł��܂��B�͂܂��Ɏ��Ă��������B��w�����̂S�{�A�T�{�Ƃ����悤�Ȕ{���ł͂Ȃ��̂ł�����B
�Ⴆ��1.5�{�̔{���Ƃ����̂́A���w���ɂƂ��Ă͍��{���Ɏv���邩������܂��A�����Ǝ����̑O��̎��A�������܂߂ĂR�l�̂����̍ʼn��ʂɂ����Ȃ�Ȃ�����i�Ȃ̂ł��B�{��1.2�{�Ȃ�Ύ������܂߂��U�l�̒��ōʼn��ʂɂȂ�Ȃ�����i���܂��B�u�ׂ̎��ȏ�̓_�����Ƃ�Ȃ�����I�v�ƋC�\����K�v�͈����܂���B
�����܂Ŏc������͂킸���ł����A���͂P���P�����ɉ߂����Ă��������ˁB
���E�� ��� [2019-02-23]
�w�N���e�X�g���߂Â��Ă��܂����B
�e���w�Z�Ńe�X�g�͈͂����\����܂����B�e�X�g�܂Ŏc���P�`�Q�T�Ԃł��B�C�����悭�V�w�N���}������悤�Ɋe���S�͂��o����܂��傤�B�e�X�g�͈͂����\����Ă��玩�K���𗘗p���钆�w���������Ă��܂����B�܂��͂��̂P�T�ԂŊe���Ȃ̃��[�N��K���I��点�܂��傤�B���ɐ��w�͂P�N�����Q�N������l�ł͂Ȃ��Ȃ�����������Ȃ���肪���[�N�Ɍf�ڂ���Ă��܂��B��ǂ�ł킩�����C�ɂȂ�����A�u�ǂ����킩�Ȃ����炢����v�Ɠ����o�����肹���ɕtⳂȂǓ\���Ă����ĉ������B�����Ɏ����Ă��ďm����u�t�̐搶��߂܂��ĉ�������悤�����낪���܂��傤�I
���E�� ��� [2019-02-16]
����e�X�g�̍���̕��@
����ɂ��́B�m�[�o�X�̍�����ł��B
�����͍���̒���e�X�g�̕��@��`���v���܂��B
���܂������̎d�����킩��Ȃ��A����Ȃ�ăZ���X�ł���A�ƌ����邱�Ƃ��������Ȃł����A����e�X�g�����Ɍ��肷��Ȃ�ΒN�ł��Z���I�ɐ��ʂ��グ�邱�Ƃ��ł��܂��B
�������w���㍑�ꂪ���Œ��P�A�Q�N���̂Ƃ��͂U�O�`�V�O�_���̓_���ɗ��܂��Ă����̂ł����A���R�ɂȂ��Ĉȉ��̕��@�ŕ��������ʁA���肵�ĂW�O�_�ȏ�̓_�����Ƃ��悤�ɂȂ�܂����B
�y�X�e�b�v�@�@�Q�O�_�˂S�O�_�z
���w�Z�̍���̒���e�X�g�̕��ɂ͒i�K������܂��B
���݂R�O�_�ȉ��̒��w���́A�܂��������K����n�߂܂��傤�B
�܂����i���ϓ_�O��͂Ƃ�Ă��鐶�k�������Ŏ�肱�ڂ��Ă��邱�Ƃ͑����ł��B�����͐���S������Ė���ē_�����グ���ĉ������B
���w�P�N���̃e�X�g�ɂ��Q�N���̃e�X�g�ɂ��K���e�X�g�͈͂ɂ͕K�������������Ă����Ǝv���܂��B�����������ɂ��ĉ������B
�����̊w�Z�Ŋ������P�O�`�R�O�_���߂Ă��܂��B
�����o���邾���œ_�������銿���́A���Ȃ��Ƒ��ł��B
�܂���ҍ�i���Ȃǂ̒m�������o���Ȃ��Ƒ��ł��B
�������o����Ƃ��̃R�c�Ƃ��āA�ǂ݂Ə����̗������o����Ɨǂ��ł��B
����͒���e�X�g�ł��������ł������ł��B
�y�������o����Ƃ��̃|�C���g�z
���������e�X�g
�Ђ�����m�[�g�ɏ����Ċo���Ă����̂������ł����A�P�x�������炷���Ƀe�X�g�����āA�ł��Ȃ����������݂̂�����x�����čĂуe�X�g�B�������������Y���ŕ������ق��������o�����܂��B
���ȏ��̉��ǂ�����ƍ���̓_�����A�b�v����I
�y�X�e�b�v�A�@�S�O�_�˂U�O�_�z
�����Ԃ������Ă���̂ɂȂ��Ȃ����т��オ��Ȃ��B����Ȑ��k�ɑ����̂��A���ǂ����Ă��Ȃ��Ƃ��������ł��B
����̃e�X�g���āA
�P�D���̕��͂́i�@�j�ɓ��Ă͂܂�ڑ������Ȃ����B
�Q�D���̕��͂́i�@�j�ɓ��Ă͂܂錾�t�������Ȃ����B
�Ƃ�����肪���\�o��Ǝv���܂��B
���̖����������߂̍ł��ȒP�ȕ��@�́A���̒������ȏ��̕��͂����̂܂ܒ@�����ނ����ł��B
���ɓ�����ōł��ȒP�ȕ��@�͉��ǂł��B
�x���ꂽ�Ǝv���Ė����̂悤�ɉ��ǂ����Ă݂Ă��������B�e�X�g�͈͂̕��͂��ׂĂ����ǂ��Ă��P���R�O���͂�����܂���B
�U�O�_�܂ł͊ȒP�ɓ_�����グ���܂���B
���������̕��@�����ԃe�X�g�Ɗ����e�X�g�ł����g���Ȃ����@�ŁA���Z�����̏ꍇ�͎�����@���قȂ�܂��̂ŁA���ӂ��ĉ������B
�y���ǂ�����Ƃ��̃|�C���g�z
�@�����̐ςݏd�˂ʼn��ǂ�����
���ǂ�����Ƃ��̃|�C���g�́A�����I�Ɍv��𗧂ĂĂ���Ă������Ƃł��B
�P���P�O����R���Ԃ����ĂR�O�ǂ���̂ł͂Ȃ��A�P���Q����P�T���Ԃ����ĂR�O�ǂ����ق����A���ɓ���₷���ł��B
�A�ٓǂł̓_���ȗ��R
���ǂ������Ȓ��w���̏ꍇ�A�ǂ����Ă��ٓǂ����悤�Ƃ��Ă��܂��̂ł�������̓_���ł��B�Ȃ��Ȃ�ٓǂ͖ڂ����g��Ȃ��̂œ��Ɏc��Ȃ�����ł��B���ǂ͌��Ǝ����g���̂ł��L���Ɏc��₷���Ȃ�܂��I
���w�Z�̍���̖��W���o����Ɠ_�����A�b�v����I
�y�X�e�b�v�B�@�U�O�_�˂W�O�_�z
���ȏ��̕��͂����ǂ�����A������x�͓��̒��ɖ{���������Ă����Ǝv���܂��B
�����A���̂悤�Ȗ��c
�R�D�������̌��t�ɂ��č�҂̍l���ɋ߂����̂��A
���̃A�`�G�̒�����I�сA�L���œ����Ȃ����B
����Ȗ�肪�o�邩�Ǝv���܂��B
����e�X�g�ł́A����������肪������O�ɏo��̂ł����A���͂�����������������Ƃ����v�����Ƃ�����܂��B
��҂̋C�����Ȃ����҂ɂ����킩��Ȃ��ł���I�I�ƁB��
���͂��̖��͐搶���l���Ă���̂ł͂Ȃ��A�v�����g����W���炻�̂܂����Ă��Ă��܂��B
���搶����҂̋C�����𗝉��ł����炷�����ł����ˁB
�ł�����A�v�����g����W�̓��������̂܂܊o���邱�ƂŁA�ȒP�ɉ����Ă��܂��܂��B
����łW�O�_�܂ł͓_�����グ���܂��B
�y�w�Z�̖��W���������̃|�C���g�z
�P��Ŋo������Ǝv�������ԈႢ�I
�悭�u�P������������̂ł����o�����Ȃ��v�ƔY��ł��钆�w��������̂ł�������͓�����O�ł��B�l�Ԃƌ����̂͌J��Ԃ��J��Ԃ����W���������Ƃł悤�₭���ɓ���悤�ɂȂ�܂��B�Œ�R������܂��傤�I
���@���ƒ����lj�͂��A�b�v�����č����_��_�����I
�y�X�e�b�v�C�@�W�O�_�˂X�T�_�z
�������Ȃ�������̒���e�X�g�ŁA�ǂ����Ă��X�O�_�ȏ��_�������Ǝv������A���ł��ǂ��̂����W���P���w�����Ă��Ă��������B�m�Ŕz�z���Ă�����K�v�����g����荞��ł��\���܂���B
���̖��W���g���ĕ��@���ƒ����lj�͂�t���Ă����ƈ�C�ɂX�O�_������悤�ɂȂ�܂��I
��{�I�ɒ��w����̒���e�X�g�ƌ����̂́A�w�Z�ŏK�����Ƃ��납��o������܂��B
�X�e�b�v�P����X�e�b�v�R�̕��@�����H����A�w�Z�ŏK�����Ƃ���͊����Ƀ}�X�^�[�ł���̂ł��B
���̕��ɉ����āA�X�e�b�v�S�̕����@�ŁA���@�������͂ƒ����������͂̉��p�͂�t���Ă������ƂŁA��C�ɂX�O�_�̑��ɏ悹�邱�Ƃ��\�ɂȂ�܂��I
���ɁA�i���̕��ނ�|�u�@�Ȃǂ̊��p�Z�@�́A�w�Z�̖��W���P�x�����������ŁA�����ɗ����ł�����̂ł͂���܂����B
���̖��W�̗��K������������Ɖ����Ă������ƂŁA���߂ĉ������̍��{�I�ȍl�����������ł���̂ŁA�ł��邾�����̕����@�ʼn��p�͂�t���Ă��������B
�܂����@�͂ƒ����lj�͂́A�����ɂ��Ȃ�����ł��̂ŁA�������������Ă����Ă����͂Ȃ��Ǝv���܂��I
���E�� ��� [2019-02-02]
<< ���̃y�[�W �O�̃y�[�W >> �ꗗ��\��
- �ʎw���m�m�[�o�X >
- ��ʌ� >
- �^��{���Z >
- ���m�点













 ���m�点�S��
���m�点�S��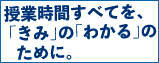


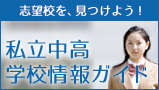

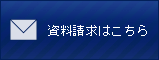
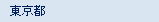
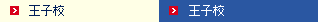
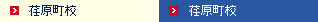
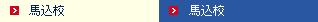
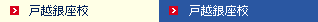
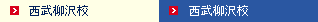
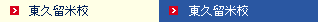
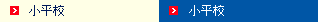
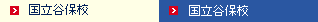
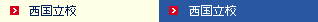
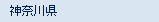
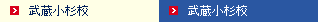
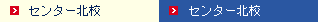
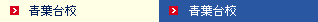
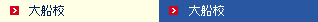
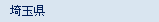
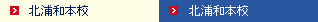
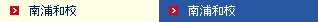
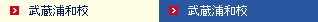
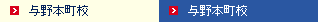
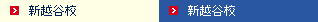
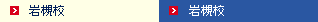
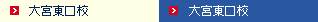
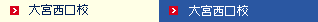
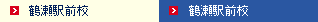
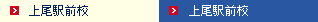
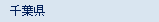
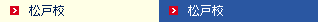
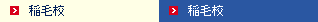
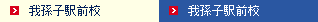
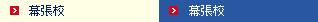
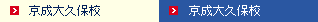
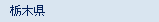
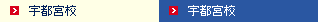
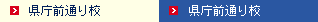
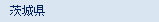
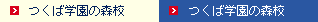
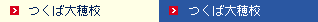
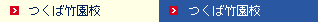
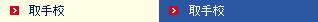
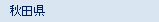
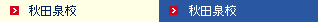
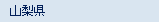
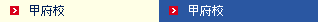
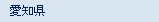
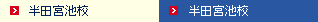
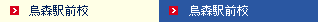
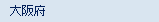
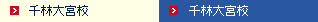
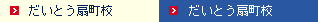
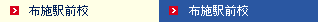
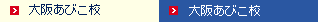
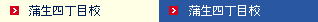
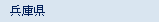
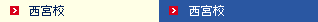
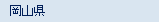
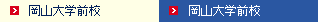
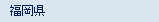
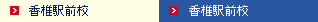
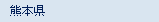
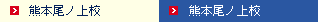

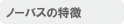

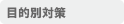




 2025-06-03
2025-06-03 2025-03-06
2025-03-06 2025-02-28
2025-02-28 2024-09-02
2024-09-02 2024-03-08
2024-03-08 2023-09-11
2023-09-11 2023-09-05
2023-09-05 2023-08-07
2023-08-07 2022-12-08
2022-12-08 2022-09-27
2022-09-27 2022-09-01
2022-09-01 2022-06-17
2022-06-17 2022-06-17
2022-06-17 2022-05-16
2022-05-16 2022-05-09
2022-05-09 2022-02-25
2022-02-25 2021-11-19
2021-11-19 2021-09-01
2021-09-01 2021-05-06
2021-05-06 2025-07-12 �����Y�a�Z
2025-07-12 �����Y�a�Z 2025-07-12 ��эZ
2025-07-12 ��эZ 2025-07-12 ���R��w�O�Z
2025-07-12 ���R��w�O�Z 2025-07-12 �`�����Z
2025-07-12 �`�����Z 2025-07-12 �����l���ڍZ
2025-07-12 �����l���ڍZ 2025-07-12 �����O�ʂ�Z
2025-07-12 �����O�ʂ�Z 2025-07-11 ���ʼnw�O�Z
2025-07-11 ���ʼnw�O�Z 2025-07-11 �����Ƃ���Z
2025-07-11 �����Ƃ���Z 2025-07-11 ��Y�a�Z
2025-07-11 ��Y�a�Z 2025-07-09 �F�s�{�Z
2025-07-09 �F�s�{�Z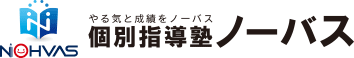


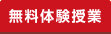

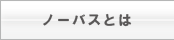

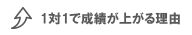

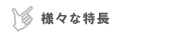
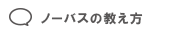
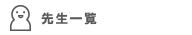

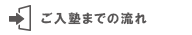

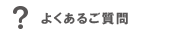
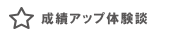
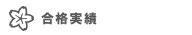
![���i�̌��L�i���R�~�E�]���j](https://www.nohvas-juku.com/library/images/menu/mainmenu_nakami_1-13.gif)