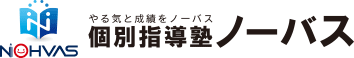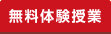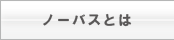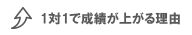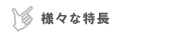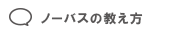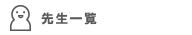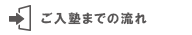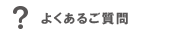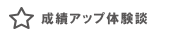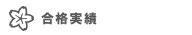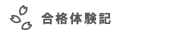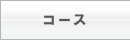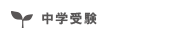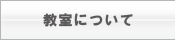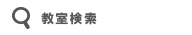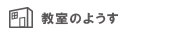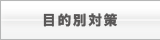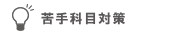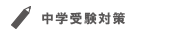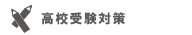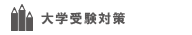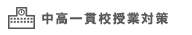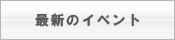お知らせ
休みの日はこの勉強サイクルで1日を過ごせ!
現在、受験シーズン真っ只中!
オミクロン株の流行で、学校がお休みになった生徒さんもいることでしょう。
しかし、入試を控えている受験生にとっては、自分の勉強に専念できるようになり、好都合の生徒さんもいることでしょう。
「学校がお休みになった。やったー、家でだらだらできるー!」という生徒さんは要注意です!
学年末テストは範囲が縮小される可能性があるにしても、必ずやってきます。
そして、お休みになったからといってサボらずに取り組んでいる生徒さんはこの期間にぐんぐん伸びていきます。
学校が休みの日などは、1日をどう過ごしていくかで変わっていきます。
今回は、1日の過ごし方のモデル例を載せておきますので、参考にしてみてくださいね。
題して、「8時間睡眠で、10時間勉強するスケジュール」
〜7:30 起床
7:30〜 8:30 勉強 1時間
ここでは、前日の復習をしましょう。 朝は、集中力の高まる時間帯なので、この時間を利用して勉強しない手はありません。 発想力も同時に高まるので、アイデアを考えるのもこの時間が最適です。 起きたばかりの時は、要注意です! まだ脳が目覚めていない状態なので、復習に当てるが無難です。 英単語の暗記や自分でまとめなおしたノートを振り返ったりすると良いです。
8:30〜10:00 朝食、身支度
10:00〜12:30 勉強 2時間30分
ここでは、苦手な教科・新しい内容に取り組みましょう。 午前中の脳が元気な時間帯に苦手な教科、新しい内容の勉強など、頭を使う勉強に取り組むと良いです。 脳のパフォーマンスが上がっている時間帯に、負荷が高い勉強をやっていきましょう! 数学、物理、化学など、計算をする科目が向いています。
12:30〜14:00 昼食、仮眠(20分がちょうど良い!)
14:00〜19:00 勉強 5時間
ここでは、得意な科目・これまでの復習を取り組みましょう。 夕方、夕食前は、脳のパフォーマンスが上がっている2回目の時間帯です。1回目と違うところは、処理能力が高まるところです。 問題集を解いたり、午前中の復習をしたり、得意な科目をやっていきましょう!
19:00〜21:00 夕食、お風呂など
21:00〜22:30 勉強 1時間30分
寝る前は暗記に特化するのにうってつけの時間です。 この時間で暗記をし、次の日の朝に復習するルーティーン(習慣)を作っていきましょう。 毎日コツコツ続けることで、長期記憶に留まります。
22:30〜23:20 明日の準備 何を勉強するかなどもある程度目標を立てておくと良いです。 やるべきことをはっきりさせておくと、翌日に迷って時間を割いてしまうということから避けることができます。
23:30〜 就寝
個別指導塾ノーバスでは先生と生徒1対1の完全個別指導で、生徒さんの成績を上げることを最大の目標とし、講師一同指導にあたっております。
進路指導においても、現状を分析し課題点を見つけ、生徒さん一人一人にあった具体的な改善策を伝授します!
また、公式サイトからのお問い合わせ限定の春のキャンペーンを実施中です。
【キャンペーン詳細】
各校先着38名様限定で入塾金が無料となります。
※定員に達し次第終了となります。
まずは、無料カウンセリング・無料体験授業にお越しください!
下記URLよりご予約が可能です!
http://www.nohvas-juku.com/cs/cs_taiken.php
個別指導塾ノーバス 大宮東口校
TEL:048-729-6515
Mail:omiyahigashi@nohvas-juku.com
勉強法 [2022-02-03]
入塾金無料キャンペーン実施中!
【キャンペーン詳細】
各校先着38名様限定で入塾金が無料となります。
※定員に達し次第終了となります。
【キャンペーン適用条件】
はじめてのお問い合わせを公式サイトフリーダイヤル(0120-546-634)または、各校舎直通番号よりご連絡いただいた方が対象となります。「公式ホームページ」を見たとお伝えください。
当サイトお問い合わせフォームからも、はじめてのお問い合わせは自動的にキャンペーンが適用となります。
※その他キャンペーンや、公式サイト以外で実施するキャンペーンと併用できないことがあります。
※一部教室はキャンペーン内容が異なる場合があります。詳細はお問い合わせください。
春期講習や、入塾前の無料体験授業も実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
個別指導塾ノーバスでは先生と生徒1対1の完全個別指導で、生徒さんの成績を上げることを最大の目標とし、講師一同指導にあたっております。
進路指導においても、現状を分析し課題点を見つけ、生徒さん一人一人にあった具体的な改善策を伝授します!
まずは、無料カウンセリング・無料体験授業にお越しください!
下記URLよりご予約が可能です!
http://www.nohvas-juku.com/cs/cs_taiken.php
個別指導塾ノーバス 大宮東口校
TEL:048-729-6515
Mail:omiyahigashi@nohvas-juku.com
教室について [2022-02-02]
覚えていれば、よりプラスに!ワンランク上へと押し上げる英単語7選
こんにちは、個別指導塾ノーバス大宮東口校です。
2月に入り、受験シーズンが本格化しました。
高校1・2年生は、学校の先輩が受験で校内からごっそりいなくなり、違和感を感じる人もいれば、寂しさを感じる人もいることでしょう。
大学受験の英語は改革されながら、難易度も大学によって様々、受験する学部によっては専門用語が扱われるなど、〜〜までを覚える。など、範囲が決まっているわけではありません。
言い換えれば、どんな英単語が出てきても、「意味がわからなければ、読むことができない」ということです。
今回は、少し難易度は高いかもしれませんが、覚えておくことで、ワンランク上へと押し上げてくれる名詞をご紹介します。
知らないから恥ずかしいということはありません。
知らなければ覚えればいいのです。そして忘れないようにインプットし、自分 の知識を増やしていきましょう。
今回は、名詞を7つ厳選しました。
1:rage
「激怒」・・・人の怒りの度合いを表すこともありますが、人以外を主語としたときに、度合いの凄さを大きく表すときにも用いられます。
Ex)The rage of nature. 「大自然の猛威」
2:encyclopedia
「百科事典」・・・”pedia”は元々ギリシア語で「教育」という意味の言葉でした。”en”は「中へ」、”cyclo”は「回転する、ぐるぐると回る」という意味合いがあります。
図鑑を読んでいる時など、図鑑。つまり「教育=知識の集合体」の中へ入ると、こっちのページへ、気付いたら、パラパラと他のページへ飛んでずっと読み耽ってしまったことはありませんか?
3:collision
「衝突」・・・野球をしている人、見ている人は、「コリジョンルール」というルールをご存知のはずです。
コリジョンルールとは、ランナーが本塁へ帰ってくる時のキャッチャーとの衝突に関するルールのことです。
AとBが物理的に衝突した時に使います。
また、AさんとBさんが意見が食い違って衝突している。といった、物理的には衝突していないが、衝突関係にある場合でも用いられます。
4:sewage
「下水」・・・下水管のことを”sewer”といいます。”age”はものを指す言葉として使われているので、直訳すると「下水管のもの」。つまりは「下水」となるわけですね。
5:monk
「僧」・・・乗り物でモノレールに乗ったことがある人は思い出してみでください。モノレールは電車のように2本のレールの上を走っているでしょうか。
いいえ、1本のレールの上を走っていますね。”mono”という言葉は、単体の物や唯一といった「一つ」を表す言葉です。
他の英単語にも、”monopoly”「独占」”monotone”「モノトーン/単調さ」などがあります。
monkも、人里離れた場所で一人で暮らす、一人で成す修行僧を表しています。
6:funeral
「葬式」・・・”funeral”は古代の葬式において、たいまつの明かりの行列を指す、”funeralis”(ラテン語)が語源とされています。
7:pollen
「花粉」・・・現在では、花粉を指しますが、もとはラテン語の”pollen”「細かい粉」という意味から来ています。身近な言葉だと”powder”「粉末/パウダー」が同義語としてあります。
毎年多くの被害者を出すとあるものがやってきますね。
「花粉症」です。私も約20年ほどの長い付き合いになります笑
花粉症は英語では”allergy to pollen”と言います。
英単語は、語源の意味を知ると、より理解が深まります。
気になった単語は、語源を調べてみると、そこから新しい発見が見つかるかもしれません。
個別指導塾ノーバスでは先生と生徒1対1の完全個別指導で、生徒さんの成績を上げることを最大の目標とし、講師一同指導にあたっております。
進路指導においても、現状を分析し課題点を見つけ、生徒さん一人一人にあった具体的な改善策を伝授します!
まずは、無料カウンセリング・無料体験授業にお越しください!
下記URLよりご予約が可能です!
http://www.nohvas-juku.com/cs/cs_taiken.php
個別指導塾ノーバス 大宮東口校
TEL:048-729-6515
Mail:omiyahigashi@nohvas-juku.com
勉強法 [2022-01-31]
私立高校入試 合格速報
私立高校の受験が終わり、結果の報告をしてくれる生徒が少しずつ出始めてきました。
現段階でわかっている、大宮東口校の生徒の中学入試&高校入試&大学入試の合格校をお知らせいたします。
※五十音順
【中学】
・大宮開成中学校
・栄東中学校
【高校】
<埼玉県>
・浦和学院高校
・浦和実業高校
・浦和麗明高校
・大宮開成高校
・春日部共栄高校
・川越東高校
・国際学院高校
・埼玉栄高校
・栄北高校
・秀明栄光高校
・昌平高校
・西武台高校
・独協埼玉高校
・花咲徳栄高校
・細田学園高校
・武南高校
<東京都>
・成立学園高校
<栃木県>
・矢板中央高校
<通信制>
・飛鳥未来きずな高校
【大学】
・北里大学 獣医学部 獣医学科
・埼玉県立大学 保健医療福祉学部 看護学科
・大東文化大学 外国語学部 日本語学科
随時更新してまいりますので、お見逃しなく!
個別指導塾ノーバスでは先生と生徒1対1の完全個別指導で、生徒さんの成績を上げることを最大の目標とし、講師一同指導にあたっております。
進路指導においても、現状を分析し課題点を見つけ、生徒さん一人一人にあった具体的な改善策を伝授します!
まずは、無料カウンセリング・無料体験授業にお越しください!
下記URLよりご予約が可能です!
http://www.nohvas-juku.com/cs/cs_taiken.php
個別指導塾ノーバス 大宮東口校
TEL:048-729-6515
Mail:omiyahigashi@nohvas-juku.com
教室について [2022-01-26]


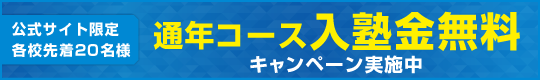










 お知らせ全て
お知らせ全て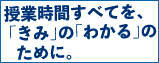



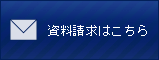
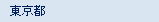
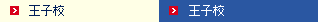
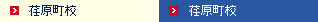
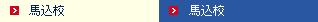
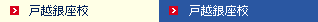
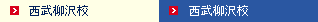
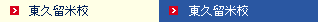
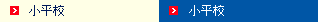
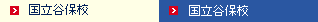
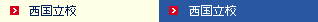
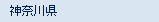
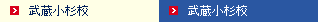
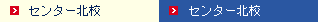
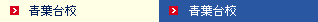
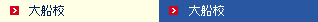
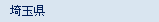
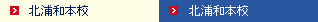
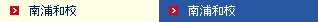
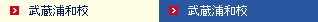
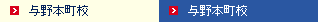
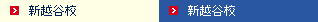
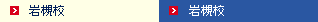
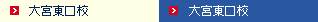
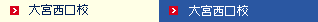
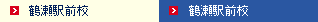
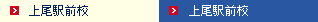
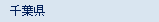
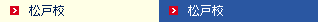
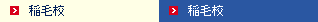
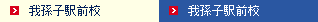
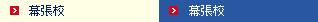
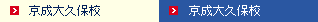
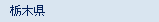
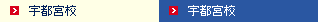
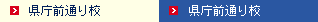
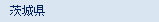
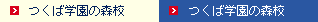
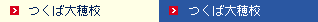
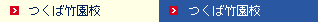
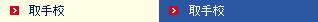
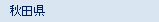
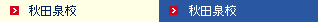
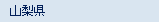
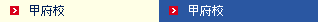
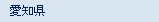
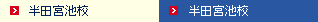
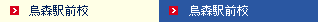
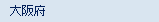
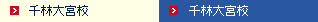
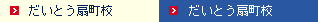
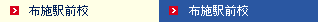
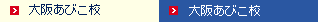
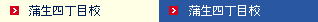
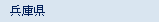
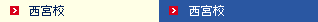
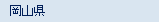
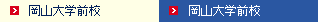
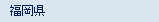
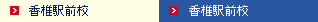
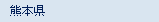
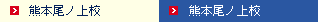

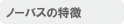

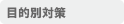




 2026-02-02
2026-02-02 2025-03-06
2025-03-06 2025-02-28
2025-02-28 2024-09-02
2024-09-02 2024-03-08
2024-03-08 2023-09-11
2023-09-11 2023-09-05
2023-09-05 2023-08-07
2023-08-07 2022-12-08
2022-12-08 2022-09-27
2022-09-27 2022-09-01
2022-09-01 2022-06-17
2022-06-17 2022-06-17
2022-06-17 2022-05-16
2022-05-16 2022-05-09
2022-05-09 2022-02-25
2022-02-25 2021-11-19
2021-11-19 2021-09-01
2021-09-01 2021-05-06
2021-05-06 2026-02-18 香椎駅前校
2026-02-18 香椎駅前校 2026-02-18 大宮西口校
2026-02-18 大宮西口校 2026-02-18 蒲生四丁目校
2026-02-18 蒲生四丁目校 2026-02-17 大宮東口校
2026-02-17 大宮東口校 2026-02-17 荏原町校
2026-02-17 荏原町校 2026-02-16 取手校
2026-02-16 取手校 2026-02-14 武蔵浦和校
2026-02-14 武蔵浦和校 2026-02-14 上尾駅前校
2026-02-14 上尾駅前校 2026-02-14 県庁前通り校
2026-02-14 県庁前通り校 2026-02-13 松戸校
2026-02-13 松戸校